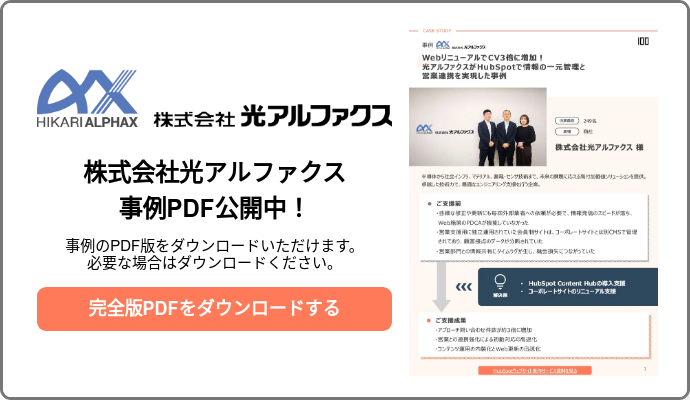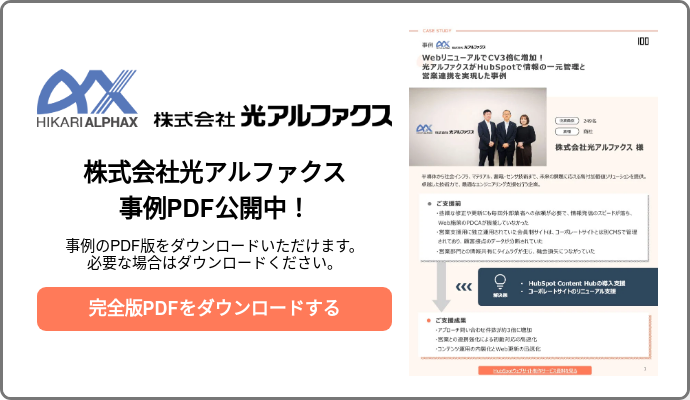WebリニューアルでCV3倍に増加!光アルファクスがHubSpotで情報の一元管理と営業連携を実現した事例

業種
商社
従業員数
101名〜300名
ご支援前の課題
・些細な修正や更新にも毎回外部業者への依頼が必要
・情報発信のスピードが落ち、Web施策のPDCAが機能していない
・営業部門との情報共有にタイムラグが生じ、機会損失につながっていた
ご支援後の成果
・問い合わせ件数が約3倍に増加
・営業との連携強化で初動対応が迅速化
・コンテンツ運用の内製化とWeb更新の迅速化
株式会社光アルファクスは、電子部品、産業機器、化学・材料の3事業を展開するBtoB商社です。製造業の現場に密着し、技術情報やノウハウを提供する提案型営業を強みとしてきましたが、新型コロナウイルス感染症による訪問営業の制限は、同社にとって営業のあり方そのものを見直す契機となりました。
非対面でも顧客との関係を維持・強化する方法を模索する中で立ち上げたのが、会員制サイト「光の知恵袋」です。そしてこの取り組みをさらに進化させるべく、情報発信の中核を担うコーポレートサイトのリニューアル、およびそれに伴うCMSの見直しに着手しました。
本事例では、コーポレートサイトのリニューアルプロジェクトを主導されたDX推進室の岡崎茂宏氏、日吉弘樹氏、五島美幸氏の3名に、プロジェクトの背景と具体的な取り組みについて伺いました。
技術と信頼で日本のものづくりを支える
ーまずは御社の事業内容についてお聞かせください
岡崎氏:弊社、株式会社光アルファクスは、大きく3つの事業部門を軸に展開している企業です。ひとつ目は電子デバイス部門で、主に半導体を中心とした製品を取り扱っています。ここは私たちの基幹的な領域であり、製造業のお客様に対して精密な技術と信頼性をもって提供しています。

(株式会社光アルファクスの製品ラインナップ)
二つ目が社会インフラ部門です。たとえば、エレベーターやエスカレーターといった人の移動を支える機械から、各種モータなどの産業用部品までを網羅しています。この領域では、実際に製造現場に入り込んで、顧客の課題に対して最適な製品とソリューションを提案するスタイルを大切にしています。
三つ目がマテリアル部門で、シリコーン素材を中心に取り扱っており、研究開発用途から実製品用まで、多岐にわたるニーズに対応しています。加えて、ここ数年では新たな成長分野として、蓄電池関連のビジネスにも注力しており、環境エネルギー分野への展開も視野に入れています。
また、製品や技術を単に売るのではなく、研究開発支援を含めたソリューション提供型の営業スタイルを強化しているのが弊社の特徴です。つまり、顧客企業の開発段階から寄り添い、パートナーとして伴走する形を理想としています。
日吉氏:弊社の取引先は基本的に製造業の企業様が中心となります。中でも工場をお持ちのメーカー様が多く、私たちの製品やサービスは、その中で活用されているケースがほとんどです。いわば、ものづくりを根底から支える存在として、専門性の高い提案が求められる現場が多いのが特徴ですね。
ー皆様が所属されているデジタル・マーケティング推進部は、どのような役割を担っているのでしょうか?
岡崎氏:デジタル・マーケティング推進部が立ち上がったのは、まさに新型コロナウイルス感染拡大の影響で、営業活動が従来通りにはいかなくなった時期です。当時、訪問営業が制限される中で、どうすれば顧客接点を持ち続けられるかという課題に直面しました。そこで生まれたのが、非対面でも営業活動を支援できる会員制サイト「光の知恵袋」の立ち上げでした。

(株式会社光アルファクス 情報サイト)
このサイトでは、従来は営業が個別に持ち歩いていたような資料やメーカー様からいただいた技術情報など、より専門性の高いコンテンツを公開し、登録者限定で閲覧できる形を整えました。そのプロジェクトがきっかけとなり、営業と連携しながらデジタルで顧客を支援するための部署としてDX推進室が設立されました。
以来、Webサイトの運営、デジタルマーケティング施策の企画・実行、さらには名刺管理ツールなどのデジタルツール導入も手掛けています。マーケティングだけではなく、実際には営業現場との連携を重視しており、メルマガの企画・配信、展示会前後の情報発信といった活動も一手に引き受けています。
日吉氏:デジタル・マーケティング推進部は、全社的なデジタルシフトを支える戦略部門として、マーケティングと営業の連携強化を軸に、Web施策の内製運用からDXツール導入・運用まで幅広い領域を担っています。Webサイトや会員制サイトの運営・改善、展示会やメルマガをはじめとする各種マーケティング施策の企画・実行、さらには名刺管理ツールを含む営業支援ツールの導入・活用支援まで、すべてを自部門で完結させる体制を構築しています。
五島氏:特徴的なのは、いわゆる分業制ではなく、5~6名の少数で全員が複数業務を横断して担当していることです。メンバー全員がWeb・マーケ・営業支援の全体像を把握しながら動くことで、各部門とスムーズに連携し、スピード感を持って施策を推進することが可能となっています。また「極力外注に頼らず、すべてを内製で行う」という方針のもと、コーディングやシステム構築まで自らの手で対応しており、限られたリソースの中でも柔軟で自走可能な運営体制を実現しています。

(五島 美幸 氏 株式会社光アルファクス デジタル・マーケティング推進部)
更新の手間、制作の遅延、機会損失、旧CMSがもたらした3つの課題
ー今回のWebサイトリニューアルの前に、どのような課題を抱えておられたのか、お聞かせいただけますか?
日吉氏:弊社が以前使用していたコーポレートサイトは、WordPressをベースにしながらも、外部の開発会社による独自のスクラッチ開発が施されていたものでした。そのため、弊社側の管理画面から直接編集できる範囲が限られており、ちょっとした文言の修正や画像の差し替えでも、外部ベンダーに依頼しなければならないという不自由さがありました。
実際、セミナー情報を掲載したり、新しいブログ記事を上げたりしたくても、都度依頼と確認の手間が発生し、結果的に情報更新が滞ってしまうことがよくありました。HTMLの知識を持っているメンバーもいましたが、毎回一からコードを書く必要があり、手間も時間もかかります。さらにスクラッチ構造ゆえに、どこをどう修正すると、全体にどう影響するかが読みにくく、表示崩れのリスクも大きいという問題がありました。
会員サイトは別のCMSを使用していましたが、今回のリニューアルを機に将来的には同じCMSで統合しようという話になりました。そのため、今回のプロジェクトのCMS選定においてはメンバーシップ機能の有無が重要な条件でした。
岡崎氏:簡単に言えば、サイト構造自体がブラックボックス化していた状態です。実は、デジタル・マーケティング推進部が発足する以前の段階で構築されたサイトだったため、現場の我々は中身の構造をまったく把握していませんでした。「どこに何の情報があるのかわからない」「誰に聞いてもわからない」という状態で、SEO対策もほぼゼロです。ページ内のテキストが画像に埋め込まれていることが多く、Googleに読み取ってもらえないという状態でした。
五島氏:私は当時からメルマガ施策なども担当していたのですが、メールのリンク先に設置するためのランディングページひとつ作るのも一苦労でした。本来なら、迅速にページを用意して、タイミングよく情報発信すべきところが、どうしても手間や工数に引っ張られて、マーケティング施策を打つこと自体が困難になっていたんです。
岡崎氏:先にもお伝えした通り、弊社は極力外注を使わない方針を取っているため、内製で運用するためにも、より柔軟で、自分たちの手に馴染むツールが必要でした。WordPressベースで構築されていた前のサイトは、やや古い印象があり、デザインやUXの観点でも、現代のデジタルマーケティングに適応しきれていないという課題もありました。
日吉氏:会員制サイトは、営業が訪問時に使う資料を補完するためのデジタル営業支援ツールとして始まりましたが、そこに掲載している技術資料やノウハウを活用して、さらに新規顧客の獲得にも活かしたいという思いが強くなってきました。そこでコーポレートサイトにこそ、情報発信と顧客獲得のための仕組みが必要だという動きが社内で起き、今回のリニューアルに向けた動きが本格化したのです。
単なるCMSではなく、営業とマーケをつなぐ統合型プラットフォームが選定の決め手に
ー新しいCMSを選ぶにあたって、どのような基準を重視されたのでしょうか?
日吉氏:大きく4つの観点で選定を進めました。一つ目は、情報更新のしやすさです。これは先ほどお話ししたように、外部ベンダーに都度依頼しなくても、自分たちの手でページを柔軟に更新・作成できるCMSであること。メルマガや展示会にあわせてLPをすぐに作れることは必須条件でした。
二つ目が、会員制サイトと連携できるメンバーシップ機能の有無です。すでに会員サイトを運用していましたが、これを将来的にはコーポレートサイトと統合したいという構想がありました。CMS単体としてだけでなく、複数の顧客接点を一元化できる仕組みが必要だったのです。
三つ目は、SEOを自分たちで管理・強化できることです。前のサイトではGoogleに読み取ってもらえない構造が多く、検索順位も上がりませんでした。Web上での新規顧客接点を増やすためにも、SEO機能が充実していて、施策の実行と改善が容易に行えるCMSが希望でした。
そして四つ目は、多言語対応機能です。弊社は国内だけでなく、海外の取引先とも日常的にやり取りを行っており、将来的にはグローバル向けの情報発信にも力を入れていきたいと考えています。そのため、CMSには標準で多言語ページを柔軟に作成・管理できる機能が備わっていることが必要でした。

(日吉 弘樹 氏 株式会社光アルファクス デジタル・マーケティング推進部)
ーCMSの候補としてはどのようなものを検討されたのでしょうか?
岡崎氏:最初の段階では、海外産のオープンソース型CMSを有力な選択肢として考えていました。理由は多言語対応がしやすいという評判を耳にしたためです。また、そのCMSを提案してくださったベンダーさんが関西の企業で、地理的な近さから迅速なやりとりがしやすかったという点も後押しになりました。
日吉氏:加えて、オープンソース型であるがゆえカスタマイズ性が高く、WordPressよりもセキュリティが高いのも魅力でした。その一方で、ある国産CMSも最終候補として有力でした。UIの使いやすさ、ノーコードでページを作成できる点、さらにベンダーによるサポート体制の安心感など、多くの点で魅力を感じていました。実際に社内でも、そのCMSで決まりというムードになっていた時期もありました。
ただ、唯一にして最大の課題がありました。それが私たちが重視していたメンバーシップ機能が搭載されていなかったことです。これを実現しようとすると、別のツールと連携させる必要があり、その点がどうしても引っかかっていたんです。
ーそのような中でHubSpotをご検討されたきっかけは何だったのでしょうか?
五島氏:国産CMSの導入と社内でもほぼ意思決定が固まりかけていたとき、再度レビューサイトを通じて情報収集をしました。そこで偶然HubSpotの名前を見つけて、調べてみたところ、私たちが求めていた4つの条件、つまり更新性・会員機能・SEO機能・多言語対応をすべて満たしている上に、さらに統合型のマーケティング機能が備わっているという点に驚きました。
日吉氏:HubSpotをより深く理解するため、公式パートナーを探しました。その中で、HubSpotの導入支援・運用支援の実績が豊富な100さんに話を聞くことにしました。実際に私と五島が面談したところ、営業連携やデータの一元管理といった、弊社の今後の方針に合致するCMSであることが明確になりました。導入を検討していた海外CMSとの比較検討でも不利な点は見当たらず、私はHubSpotの導入を社内に強く提案しました。
岡崎氏:打ち合わせから戻った2人が熱意を持ってHubSpotを勧めてきた姿が印象的でした。そこまでいうのであれば、私としても検討しないわけにはいきません。実際に調査を進める中で、HubSpotの汎用性に強く惹かれました。WordPressなどのようにCMS単体の機能にとどまらず、メール配信や顧客管理、営業との連携といったマーケティング機能が統合されたプラットフォームである点が魅力的だったのです。まさに、弊社が目指す将来像に合致していました。
中でも、顧客情報をシームレスに管理できる点が決め手となりました。これまで実現できていなかった、接点情報の集約や効率的なアプローチも、HubSpotなら可能だと確信しました。
当時、名刺管理ツールとしてSansanは導入していたものの、それ以外の顧客管理は整備されておらず、営業担当が各自でExcelやスプレッドシートを使って管理していました。結果として、部署間の連携や情報の一元化には課題が残っていたのです。
そうした現状を踏まえると、HubSpotであれば、Sansanとの連携も可能であり、顧客情報、行動履歴、問い合わせ対応など、すべての情報をひとつのプラットフォームに集約できるという点で、他のCMSとは一線を画していると感じました。

(岡崎 茂宏 氏 株式会社光アルファクス デジタル・マーケティング推進部)
谷脇(ハンドレッド):HubSpotとSansanを連携することで、名刺情報を両ツール間で自動的に同期できるようになります。これにより、業務の効率化や情報の重複防止といった多くの利点が得られますが、最大の成果は、名刺情報を活用可能なデータ資産として運用できる点にあります。
たとえば、営業がSansanで取り込んだ名刺情報を、マーケティング担当がHubSpot上で確認し、対象ごとにセグメントを分けたメール配信が可能になります。営業とマーケティングの連携が成果に直結する光アルファクス様のような企業では、非常に有用な機能だといえるでしょう。

五島氏:HubSpotはこれまで検討してきたCMSの中で最も多機能で、そこも大きな魅力でした。アクセス解析やコンバージョン管理といったマーケティング施策の可視化機能も充実しており、「実現したくても叶っていなかったこと」が確実に形にできるという手応えを感じました。
数あるCMSの中でも、「HubSpotに最も将来性を感じ、自社内で運用できるという確信を持てたことが、最終的な決め手となりました。
内製×伴走支援で半年でローンチしたコーポレートサイトのリニューアル
ー本プロジェクトの内容についてお聞かせください
谷脇(ハンドレッド):まずはペルソナの再設計をしました。誰に向けて情報を発信するのか、どのような課題やニーズを持つターゲットに価値を届けるのか、そうした視点をチーム全体で再認識することで、Webサイト全体の構成やコンテンツ設計にも明確な軸が生まれます。
HubSpotのような統合型プラットフォームを最大限に活用するには、CMSを切り替えるだけでは不十分で、情報を届けたい相手の定義とその行動導線の設計が欠かせません。光アルファクス様のように、技術系のBtoB商材を扱う企業では、営業支援や製品理解の精度が成果に直結するため、ペルソナを起点とした設計が成果に大きく貢献したと感じています。

(ウェブサイトリニューアル時に再構築したペルソナの例)
岡崎氏:私たちはコストを重視したため、柔軟な支援体制をお願いしました。通常であればベンダーにフル構築を任せるところですが、初期段階ではひな形となるページのみ作成していただき、その後の複製・展開は自分たちで進める方式を採用しました。
また、プロジェクトの納期を半年でリリースと明確に定めていたため、そのスケジュールに沿って、5名体制で全ページの構築を行いました。HubSpotの操作は初めてだったこともあり、当初は仕様の把握に苦労しましたが、不明点があれば100さんにすぐ相談でき、迅速な回答をいただけたことで、大きな混乱なくプロジェクトを進行できました。
五島氏:もともとHTMLなどの基礎知識はありましたが、HubSpotのようにドラッグ&ドロップ操作機能を活用したCMSは初めての取り組みでした。テンプレート構造やモジュール設計の自由度が高く、操作に慣れるにつれて効率的にページを制作できるようになりました。
公開前に基本的な操作方法を社内で習得できたこともあり、リリース後はすぐにブログ記事の更新やランディングページの作成にも取りかかれる体制が整っていました。
日吉氏:Webリニューアルを推進するため、社内にプロジェクトチームを立ち上げ、各部門からメンバーを選出して毎月定例会を開催しました。現場の声やニーズを反映させながら、単なる情報の棚卸しにとどまらず、お客様にとって価値あるWebサイトとは何かを意識して、構成やコンテンツを見直していきました。
中でも注力した施策の一つが、有益な情報発信です。ブログ形式で記事を継続的に公開し、検索流入の強化と顧客とのエンゲージメント向上を目指しました。製品に関連する技術情報や導入ノウハウといった製造業向けの実践的なテーマを軸に据えた結果、短期間で月間4,000件を超えるアクセスを獲得しています。
岡崎氏:WebサイトをDXの中核ツールとして位置づけた以上、マーケティング部門だけで完結するものではありませんでした。だからこそ、社内に協力者を増やし、共通の目的意識を持つことが重要だったと考えています。その点でも、プロジェクト型の推進体制は非常に効果的であり、現在もその枠組みを活用し続けています。
ー実際にHubSpotを導入してみての感想はいかがでしょうか
五島氏:HubSpotを導入して本当によかったと実感しています。これは日々の業務を通じて自然と感じることです。ページの作成は格段にしやすくなり、リード情報の管理も大幅に効率化されました。
今回、CMSに加えてMarketing Hubのプロフェッショナルプランも導入したことで、ワークフロー機能などの活用が可能になり、これまで構想段階にあった施策が次々と実現しています。こうした価値は、実際に導入してみて初めて実感できるものでした。
日吉氏:大きく実感しているのは、営業部門との連携が格段にスムーズになったことです。たとえば、資料がダウンロードされた際には、その情報を即座に営業担当へ共有できるようになりました。従来はログを取得しても、別途メールでテキストにまとめて送る必要があり、どうしても時間や手間がかかっていました。
現在は、HubSpot上でリンクを共有するだけで、簡単に確認できるようになり、自動通知の設定も活用できるため、情報連携のスピードと正確性が大きく向上しています。
岡崎氏:アクセスログの共有に関しても、同様の改善が見られました。現在は別のMAツールも併用していますが、そのツールは営業部門がアクセスログを閲覧できないため、通知の際にリンクを添付することもできません。そのため、従来はログ情報を手作業でまとめ、営業へメールで共有する必要がありました。
一方、HubSpotに移行してからは、営業担当も自ら情報を確認できるようになり、迅速な対応が可能になりました。情報共有の負荷が軽減され、業務効率が大きく向上しています。
五島氏:現在は、閲覧できるのは営業メンバーほぼ全員の約180名で、その一部には書き込みや編集権限があります。従来のMAツールでは管理者権限に制限があり、閲覧可能な人数が限られていたため、営業全体での情報共有が困難でした。その点、HubSpotは権限管理の柔軟性に優れており、部署を横断した情報共有がスムーズに行えるようになったことも、大きなメリットの一つです。
谷脇(ハンドレッド):BtoB企業をはじめ、高額商材を扱う企業においては、マーケティングと営業がいかに円滑に連携できるかが成果を左右する重要な要素となります。しかし、両部門の連携に課題を抱える企業は少なくありません。たとえば、ウェビナーで購買意欲の高いリードを獲得しても、インサイドセールスや営業との連携が不十分であれば、熱量が高いうちのアプローチを逃し、機会損失につながる恐れがあります。
その点、HubSpotでは各種ソフトウェアがCRMと標準で連携しているため、部門間で集約した顧客情報をスムーズに共有し、一貫した顧客体験を提供することが可能です。こうした連携のしやすさに価値を感じていただけていることを、私たちも非常に嬉しく思います。
3ヶ月でコンバージョン3倍。営業とマーケの連携で初動対応までのスピードが大幅に短縮
ーHubSpotを導入されてしばらく経った今、実際にどのような成果を実感されていますか?
日吉氏:まず何よりも実感しているのは、更新のしやすさが格段に向上したことです。以前は、ちょっとしたテキストの修正や画像の差し替えでもベンダーに依頼する必要がありましたが、現在は自社内で自由に編集・追加できるようになり、情報発信のスピードが大幅に向上しました。
大きな変化があったのは、ブログ記事の運用です。従来はブログ自体が存在せず、情報発信に高いハードルがありましたが、現在は「お役立ち情報」として、製品に関連する内容や業界トピックスを定期的に発信できるようになりました。
本格的なSEOに取り組み始めたのは最近ですが、すでにいくつかのキーワードで上位表示されるようになっており、着実な成果が見え始めています。

(情報発信の重要チャネルとなっているブログ)
五島氏:もうひとつ大きな成果として挙げられるのが、営業部門とのリアルタイムな情報共有が実現した点です。従来は、お問い合わせや資料ダウンロードがあっても、一度マーケティング部門が内容を受け取り、営業に転送する必要がありました。現在は、HubSpot上で営業担当者へ即時通知が送られるため、初動対応のスピードが飛躍的に向上しています。
具体的には、以前は初回接触までに半日から1日以上を要していたのが、導入後は即日対応が可能となり、お客様との距離感が大きく縮まりました。この変化は、営業部門からも高く評価されています。
岡崎氏:数値にも明確な成果が表れています。ウェブサイトリニューアル前後の3ヶ月間を比較すると、お問い合わせ件数は約3倍に増加しました。リニューアル前(8〜10月)の25件に対し、リニューアル後(11月〜1月)は70件に達しています。

(ウェブサイトリニューアル前後でのCV数)
これは単なるページ閲覧数の増加ではなく、コンバージョンに直結する成果が大幅に向上したことを意味しており、情報発信の強化と導線設計の工夫が効果を発揮した結果といえるでしょう。さらに、今回新たに導入した資料ダウンロード機能により、新たなコンバージョンポイントが生まれました。その接点を起点に、営業部門が実際の商談創出へとつなげる動きも見られるようになっています。
日吉氏:加えて、マーケティング活動の効果を定量的に可視化できるようになったことも、大きな成果の一つです。従来はコンバージョン数の測定や報告が行われておらず、施策の有効性が不明瞭なまま進行していました。現在は、ダウンロード数や問い合わせ件数に加え、それらが商談につながっているかどうかまでを社内でリスト化し、定期的に報告する体制が整っています。
有効だったのが、HubSpotのフォーム管理機能です。フォームごとに成果を可視化できるため、各資料のパフォーマンスをひと目で把握できます。以前は、お問い合わせフォームが1種類のみで、資料別のコンバージョン数は手作業で集計していましたが、現在は部署ごとに入力項目を精査・設計することで、「どの資料が多くダウンロードされているか」「どの入力項目が離脱の要因か」といった情報を数値で説得力をもって共有できるようになりました。

実際の会議でも、HubSpotのレポート画面をそのまま表示しながら議論ができるため、感覚的な判断ではなく、データにもとづいた意思決定が可能になっています。以前は、管理画面にデータが蓄積されているだけで、出力や可視化が難しく、強化すべきポイントの特定が困難でした。この改善により、組織全体でのマーケティング施策の精度も着実に高まっています。
五島氏:リニューアル前後でコンバージョン数は約3倍に増加しましたが、さらなる成果の伸びしろを強く感じています。HubSpotを通じて取り組むべき施策はまだ多く、やりきれていない部分も多々ある中で、これだけの成果を出せたことに対して、今後の展開に大きな期待を寄せています。
岡崎氏:今回のプロジェクトを通じて、Webを活用すれば成果が出るという実感が社内に浸透しました。Webリニューアルを契機にデジタルマーケティングへの理解が深まり、社内の協力者が増えたことは、大きな副次的効果です。現在では部門を横断した連携も生まれ、マーケティング施策の幅が着実に広がっています。
バラバラだったデータをすべてつなぐ。次なる目標は全社連携
ー今後の展望についてお聞かせください。
岡崎氏:私たちがHubSpotを選定した最大の理由は、CMSとして他の選択肢よりも優れていた点にあります。UIの扱いやすさ、ページ作成の柔軟性、SEOをはじめとする基本機能の充実度は高く、導入初期から安心して運用を進められました。
導入を進める中で実感したのは、HubSpotが統合型プラットフォームとして持つ可能性です。当初は「海外製で高価なのではないか」といった先入観もありましたが、実際にはメール配信や会員管理などの機能が標準で搭載されており、むしろ国内ツールと比較してもコストパフォーマンスに優れる部分が多く見受けられました。
現在は、社内データの統合を本格的に推進するフェーズに入っています。まずは既存のMAツールをMarketing Hubのプロフェッショナルプランへ移行し、マーケティング機能の一元化を進行中です。さらに来年には、別CMSで運用している会員制サイトもHubSpotに統合し、全社的な顧客情報の一元管理を実現したいと考えています。

(HubSpot Content Hubのメンバーシップ機能)
五島氏:MAツールの一本化は現在進行中ですが、すでに多くの可能性を感じています。中でも特に大きな変化は、ライフサイクルステージの管理が可能になったことです。従来のMAツールでは設定が難しかったステージ分類も、HubSpotではワークフロー機能を活用することで柔軟に設計できます。そのため、どこまでをマーケティングが担い、どの段階で営業に引き継ぐのかという役割の明確な可視化が進むと考えています。
これまでは、メール配信を既存MAツールで行い、アクセスログの分析は別のツールで確認するという分断された運用となっており、それぞれの施策の関連性を把握することが困難でした。たとえば、あるメルマガがどのような反応を生み、どのページへのアクセスを誘導したのか、さらにそれが具体的な引き合いにつながったのかといった一連の流れは見えにくい状態でした。
今後は、HubSpot上でメルマガ配信から顧客の行動追跡までを一元的に管理できるようになります。これにより、成果に直結する施策やボトルネックとなっている施策を特定し、マーケティングのROIを具体的なデータにもとづいて判断できる環境の構築に期待しています。
日吉氏:営業部門との連携も一層スムーズになると考えています。HubSpot上でメルマガの配信履歴や反応状況を確認できるため、営業担当も顧客の興味関心をリアルタイムで把握できるようになります。従来は施策の結果がマーケティング部門内で完結してしまうケースも多くありましたが、今後は情報の全社的な共有が進み、マーケティングから営業へのシームレスな引き継ぎの実現に向けて動きたいです。
また、現在弊社にはSFA(営業支援ツール)が未導入であり、顧客情報の管理や商談進捗が属人的になっているという課題も抱えています。
その解消に向け、長期的にはHubSpotのSales Hubを活用し、名刺管理、問い合わせ履歴、資料ダウンロード、サイトアクセスなど、あらゆる顧客接点データを一元管理できる仕組みを構築していく計画です。マーケティングから営業、そして受注・売上までを一気通貫で可視化する基盤として活用していきたいと考えています。
五島氏:最終的な目標として、2年後を目処に基幹システムの刷新も計画しており、その際にはデータウェアハウスとHubSpotを連携させて、売上・仕入・在庫といった業務データと、営業・マーケティングの顧客行動データの一元化を図る構想です。いわば、HubSpotをデジタル基盤の中心と位置づけ、社内のあらゆる情報を統合・可視化することを目指しています。
従来はデータが部門ごとに分断されており、営業・マーケティングの双方で見るべき情報や正しい情報が把握できないという状況がありました。今後は、HubSpotを中核として、営業担当がHubSpotを見れば顧客の全体像が把握できる状態を実現していきたいと考えています。
岡崎氏:今年4月から情報システム部門も兼務するDX推進室が新設されました。基幹システムとマーケティング基盤は部署こそ異なりますが、目指すべきゴールは同じです。それは、すべての意思決定をデータに基づいて行う「データ経営」の実現です。社内にその体制を築くことこそが、DX推進室に課せられた最大のミッションだと捉えています。
※記事中の部署名、役職名等は取材時のものです。
We are HubSpot LOVERS
ビジネスの成長プラットフォームとしての魅力はもちろん、
HubSpotのインバウンドマーケティングという考え方、
顧客に対する心の寄せ方、ゆるぎなく、そしてやわらかい哲学。
そのすべてに惹かれて、HubSpotのパートナー、
エキスパートとして取り組んでいます。
HubSpotのこと、マーケティング設計・運用、
組織の構築など、どんなことでもお問い合わせください。